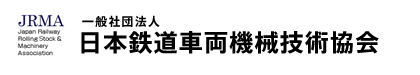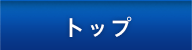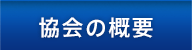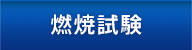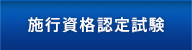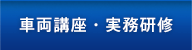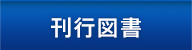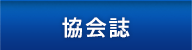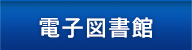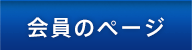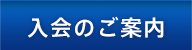トピックス
セミナー
2025年度「車両と機械」技術セミナーの開催
本セミナーは、鉄道関係業務のうち、鉄道車両及び鉄道周辺機械設備に関連しておられる 技術者の方々を対象に開講しています。保守・設計・開発をしている関係技術者の方々の業務上 での参考になることを目的としたものです。講演テーマは前記の鉄道車両及び鉄道周辺機械設備 に関連するものから、基礎知識的に必要と桃われる分野、最近話題になっている先端技術分野の ことまで、幅広い分野のテーマを取り上げています。今年度も下記のとおり、4回に分けて8テーマ を計画しておりますので、多数の皆様にご参加頂きますようご案内します。
記
1. 開催日時および演題・講師
第1回 9月 5日(金) 13:30~16:45
No.1 東京地下鉄における保安装置の変遷とCBTCの運用開始
東京地下鉄株式会社 鉄道本部車両部設計課
課長補佐 後藤 亮介 様
No.2 鉄道車両向け同期リラクタンスモータシステム
三菱電機株式会社 モビリティインフラシステム事業部
統合エンジニアリング部 車両システム技術グループ
サブグループマネージャー 金子 健太 様
第2回 10月3日(金) 13:30~16:45
No.3 誘導障害試験における現状と目指すべき方向性について
~誘導障害に関する調査研究WGより~
東京地下鉄株式会社 鉄道本部車両部設計課
設計課長 栗原 純 様
公益財団法人 鉄道総合技術研究所
車両技術研究部駆動システム主任研究員(上級)廿日出 悟 様
No.4 ブレーキシステム・制輪子の現状課題およびその対応
~ブレーキ力を変化させる要因に関する調査研究WGより~
東急電鉄株式会社 鉄道事業本部 車両部
統括部長 門田 吉人 様
公益財団法人鉄道総合技術研究所 車両技術研究部 ブレーキシステム
研究室長 中澤 伸一 様
第3回 11月 7日(金) 13:30~16:45
No.5 水素燃料電池鉄道車両に関する技術基準等の整備
国土交通省 鉄道局
技術企画課 専門官 遠藤 康信 様
No.6 東海道新幹線N700Sにおける営業車検測の実現について
東海旅客鉄道株式会社 執行役員
新幹線鉄道事業本部副本部長・車両部長 古屋 政嗣 様
第4回 12月4日(木) 13:30~16:45
No.7 TAKANAWA GATEWAY CITYにおけるCO2排出量実質0の取り組み
東日本旅客鉄道株式会社 グループ経営戦略本部
品川・大規模プロジェクト推進部門
都市計画・エネルギー・企画UT 主務 高橋 和也 様
No.8 首都圏の自動改札に挑戦した人々
一般社団法人 日本鉄道車両機械技術協会
機械部長 鈴木 直利 様
2.場 所 日比谷図書文化館 日比谷コンベンションホール(大ホール) 東京都千代田区日比谷公園1-4 ℡ 03-3502-3340
3.募集人員 各回100名(定員に達し次第締切とさせて頂きます。)
4.参 加 費
(1) 4回連続聴講の場合は31,350円/4回分一括払いです。(税込価格)
(4回分でお申し込みの場合、会員・会員外の方の参加費は同じです。
また4回分一括払いの聴講券で一度に4名までの聴講ができますので、
参加される御希望回を選定してください。)
(2) 1回毎の聴講の場合は8,800円です。会員以外の方は10,450円です。
(いずれも税込価格)
5.参加申込み
(1)E-mailにより参加者または申込者の会社、所属、連絡先住所、メール
アドレスおよび電話番号を記載のうえお申込み下さい。
参加費のお支払いは、参加者または申込者への受講票の送付と合わせて
お知らせ致します。
(2)申込先 〒105-0003 東京都港区西新橋1-19-4 難波ビル5F
(一社)日本鉄道車両機械技術協会
担当 企画部 湯本 昇
E-mail: yumoto-n@rma.or.jp
TEL 03-3593-5611
FAX 03-3593-5613
6.申 込 書
申し込み時のお願い
4回連続聴講券は1回ごと1枚づつでも、特定の1回に4名様聴講でも、
いかようにも分割可能です。
ただし、申し込みの際に実際に聴講する回と人員を『申込別』の欄に記入して下さい。
【講演概要】 (第1回 9月5日) No.1 東京地下鉄における保安装置の変遷とCBTCの運用開始 東京地下鉄では開業当初から現在に至るまで、様々な保安装置が導入され てきました。初期のシステムは、主に信号機による運行管理が中心でしたが、 技術の進歩とともにより高度な安全対策が求められるようになりました。こ れに伴い、保安装置とそれを取り巻くシステムは高度化の一途をたどり、自 動列車制御システム(ATC)や自動列車運転システム(ATO)が開発・導入さ れることで、運行の安全性・安定性が飛躍的に高まりました。そして、2024 年12月、東京地下鉄は日本の地下鉄では初となる無線式列車制御システム (CBTCシステム)を丸ノ内線全線に導入しました。CBTCは列車と地上設備間 の通信を基にした運行管理システムであり、列車位置をリアルタイムに把握 可能であることから、従来の固定閉塞ではなく移動閉塞を採用可能であるた め、列車間隔の短縮及び運行の効率化を図ることができます。本講演では、 東京地下鉄における保安装置の変遷とCBTCの概要及び効果等についてご紹介 します。
No.2 鉄道車両向け同期リラクタンスモータシステム 近年、地球環境の変化に関する課題に対し、カーボンニュートラルの実現 に向けた新技術の取り組みが加速しており、環境性能が高いとされる鉄道分 野でも、多くの電力を使用する点や、モーダルシフトによる鉄道利用促進も 期待されることから、CO₂排出量削減に向けた省エネルギー化の必要性が高ま っています。また、エネルギー需給の変化やレアアースなどの希少材料の調 達リスクも増大しており、省エネルギー化に加え、省資源化や供給の安定性 確保も重要な課題となっています。 このような背景のもと、当社ではレアアースを使用せずに高効率化を実現 する同期リラクタンスモータと、それを可変速制御するインバータ制御シス テム「SynTRACS®(シントラックス, Synchronous reluctance motor and inverter TRACtion System)」を開発しました。さらに、東京地下鉄株式会社 様と共同で、世界初となる営業線での実証試験に成功しました。その後、製 品として量産を開始し、複数の事業者様で営業車両への本格導入と運用が始 まりました。 本講演では、SynTRACS®の製品開発や特徴、東京メトロ日比谷線での長期実 証試験の内容に加え、福岡市交通局での製品適用に向けた取り組みや、シス テムの応用事例、今後の展望についてご紹介します。
(第2回 10月3日) 鉄道の安全確保に関する諸問題は極めてプライオリティの高いテーマであ るが、安全を主題とし、鉄道事業者ならびに関連機器メーカーが横断的かつ 継続的に調査研究する機会は非常に少ない。 当協会では、車両の安全問題を扱う「車両安全技術委員会」を2015年 度より新設し、その分科会組織として「安全性向上調査研究部門」を備え、 車両の動的側面及び技術的境界問題を切り口とする調査研究を行ってきた。 昨年度まで活動した2件の調査研究WGの活動成果として講演を行う。
No.3 誘導障害試験における現状と目指すべき方向性について ~誘導障害に関する調査研究WGより~ 近年、VVVFインバータやSIVといった車上機器から発生する電磁ノイズに より、地上信号装置への影響が懸念され、試験結果が鉄道運行計画に大きな 影響を及ぼすことがある。車両と信号装置の境界領域で生じる事象であるこ とから、関係する鉄道事業者、車両関係メーカー、信号関係メーカー、研究 機関等が一堂に会し、2022年度から3年間にわたり「誘導障害に関する 調査研究WG」に取り組んだ。WGではこれまでの試験方法や評価基準、対策事 例を整理し、試験の効率化や車両製造の計画段階からの予見性向上を図るた めの提案を取り纏めた。 本講演では、その要点と今後業界全体で構築すべき持続可能な方策につい て紹介したい。
No.4 ブレーキシステム・制輪子の現状課題およびその対応 ~ブレーキ力を変化させる要因に関する調査研究WGより~ 2014年2月に東急東横線元住吉駅構内において発生した電車衝突脱線 事故をきっかけに、部門の活動として、「冬期におけるブレーキ性能に関する 調査研究」および「ブレーキ・制輪子安全性向上WG」を実施してきた。そし て、さらなる安全性向上に資する課題として、最近の主流である全電気ブレ ーキ式の車両でときおり発生する、雨天時等に安定した減速度が得られない 事象に注目し、2022年度から3年間にわたり「ブレーキ力を変化させる 要因に関する調査研究WG」に取り組んだ。 本講演では、WG活動を通じて鉄道事業者が取り組んだ実例等をもとに、ブ レーキ力を変化させる要因とその対策について得られた知見を、主に車両の ブレーキ設計・製造およびメンテナンスに関わる実務者に向けて紹介したい。
(第3回 11月7日) No.5 水素燃料電池鉄道車両の技術基準の整備 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、鉄道分野の脱炭素化に関す る技術開発が進められている。 その中の一つの施策として、化石燃料を動力源としたディーゼル車両から、 水素を燃料とする鉄道車両に置き換えることで、CO2等の排出削減を目指す脱 炭素化の取組みが進められている。 水素ガスという圧力の高い可燃性ガスを使用するため、安全性の担保は不 可欠であり、想定されるリスクに応じた安全対策等が重要となる。 そこで、有識者から構成される「水素燃料電池鉄道車両等の安全性検証検討 会」を設置し、安全性の検証及び必要となる安全対策を検討することにより、 必要となる技術基準案が提案された。 また、水素ガス容器等には高圧ガス保安法が適用され、それらを鉄道車両 に搭載する際には特別認可等の特別な取扱いが必要であり、鉄道事業者の負 担が大きかったが、高圧ガス保安法の関連法令を整備し、高圧ガス保安法上 の技術基準の内容を鉄道の技術基準に移管することにより、特別認可を不要 とする等の手続きの合理化を図ることができた。
No.6 東海道新幹線N700Sにおける営業車検測の実現について 東海道新幹線では、検測専用の車両であるドクターイエローにより、軌道 や電気設備の定期検測を実施してきた。 平成13年には700系ベースのT4編成を導入し、高速走行での検測を可能 にする等の進化を遂げてきた。 一方、当社では床下機器の小型・軽量化に関する技術開発を継続的に行い、 新規機能を搭載するためのスペースや重量余裕の確保に取り組んできた。 これに加え、営業車に搭載可能な検測機器の開発や検測データの記録と伝送 強化に取り組むことで、営業車での検測が可能な技術基盤を構築してきた。 このような不断の技術開発により、営業車への検測機器の搭載を実現し、 高頻度な設備点検とタイムリーな保守作業を可能とする計画である。屋根上 や床下に検測機器を搭載するが、極力他の営業車の仕様から大きく乖離しな いよう、碍子オオイの工夫や床下機器配置の一部見直し等の工夫により必要 な機器の搭載を実現した。本講演では、これらの取組みについて紹介する。
(第4回 12月4日) No.7 TAKANAWA GATEWAY CITYにおけるCO2排出量実質0の取り組み 東日本旅客鉄道株式会社(以下 JR東日本)は、山手線で49年ぶりの新駅 として高輪ゲートウェイ駅を2020年3月に開業しました。高輪ゲートウェイ 駅が位置する田町駅-品川駅間は、従前は鉄道輸送を支える一大車両基地と して日本の成長を支える重要な拠点として機能していましたが、東海道新幹 線開業や寝台列車の廃止など、輸送体系が時代とともに変化する中、2009年 から7回にわたる大規模な線路切替工事を経て、機能移転を行うなど車両基 地改良を行うことで、将来の鉄道を支える車両基地として生まれ変わり、か つ再編により用地が生み出されました。 この開発地区の街の名称を「TAKANAWA GATEWAY CITY」に決定し、「100年 先の心豊かなくらしのための実験場」となるまちを目指しています。 本講演では、JR東日本グループが掲げる環境長期目標「ゼロカーボン・チ ャレンジ2050」の先導プロジェクトとして、環境先導のまちづくりを目指す TAKANAWA GATEWAY CITYが取り組む環境・エネルギー技術の事例を紹介します。
No.8 首都圏の自動改札に挑戦した人々 今日の自動改札の進化は目覚ましく、21世紀に入った年から始まった非接 触ICカードからは、格段にサービスの形態が変化してきている。 この基礎となったのは、1990年から展開された首都圏の自動改札であった ことを忘れてはならない。20年以上も経過した磁気式ではあったが、高保磁 力、FM方式の新しいエンコードフォーマット、ストアードフェア、不正乗車 対策などの新しい技術、新しいサービスを導入して社会インフラとして定着 させた。 国鉄時代から、首都圏への自動改札導入については、国鉄、公民鉄の連絡 運輸や相互直通乗入れが多く、複雑な路線形態になっていることから導入は 難しく不可能とさえ言われ、同時に国鉄は労働組合との対立により進展しな いことから、実施しようとする人は誰一人としていなかった。 本講演では、1987年の国鉄分割民営化により新会社の誕生が契機となって、 最難関であった首都圏の自動改札に挑戦する人々が現れ、周到な計画のもと 見事にやり遂げたその足跡を伝えていく。