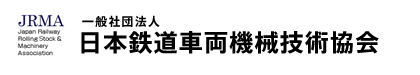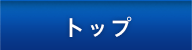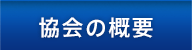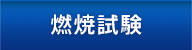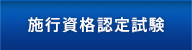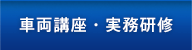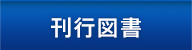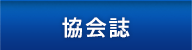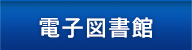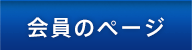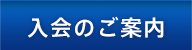活動実績
業務活動実績
24年度の業務活動実績
1.調査研究及び試験事業等
[ 自主事業 ]
(1) 車両関係
平成24年度は、車両委員会の下で以下の活動を実施した。
- ア.車両に係る品質向上
平成23年度に引き続き、品質向上に関する部会テーマとして、「電子機器装置の検修における信頼性向上の取り組み」について作業部会を開催し、現状把握・対策案等の議論・検討を行った。
- イ.車両に係る技術継承
平成23年度に引き続き、車両に係る技術継承作業部会テーマとして、執筆者等の経験やノウハウを伝承するため「主回路シリーズ(主電動機編)」の出版物を刊行することを目的とし、執筆活動、編集を行う作業部会を開催して年度末に計画通り刊行した。
以上の他、従来から実施しているテーマについて以下のように取り組んだ。
- ウ.鉄道事業者共通課題の調査検討
関東・中部地区の車両担当課長を中心とした定期的な連絡会議を、2ヶ月に1回開催し、技術情報、保守情報、故障情報などの活発な情報交換を行った。
また、関西地区では関西支部主催の7社からなる車両担当者連絡会において、情報交換や問題抽出などを開催した。
- エ.電子機器等の誤動作防止に関する研究会への協力
湘南モノレール事故に関する運輸安全委員会の意見に対し、事業者及び設計製造会社等の電子機器等の故障防止関係の情報の共有化を目的としたノウハウ集を整備する研究会が国土交通省に設置されたが、当協会はその事務局として、引き続き研究会に提示する資料のデータ分析及び取りまとめ等を行った。
- オ.車両関係工事施行技術者資格認定制度の見直し
車両関係工事施行技術者資格認定制度に関して、JR各社と再度認定試験の受委託関係の覚書を締結し、運用管理者との定期的な会議を開催し、テキストの見直しや制度そのものの見直し改善等の検討を進めた。
(2) 機械関係
平成24年度は、機械委員会の下で、策定された中長期ビジョンに則り下記の活動を実施した。
- ア.機械企画小委員会
教育及び知識普及活動の一環として、若手機械関係社員を対象とした技術伝承についての研修会を行った。本年度は13名の参加者を得たが、平成20年度の開始から聴講生は計65名となった。
- イ.エネルギーマネジメント技術小委員会
近年、鉄道施設の中小規模建物の空調設備に多く用いられているビルマルチエアコンは、必ずしも効率的に運転されているとは言えない状況である。今年度はその状況に着目し、具体的なビルを選定してビルマルチエアコンの性能検証を実施し、その結果を踏まえ、今後の活動方針を策定した。
- ウ.機械設備メンテナンス技術小委員会
鉄道駅の昇降機・ホームドアの設置状況やセンシング状況を調査し、これらについて報告書「鉄道駅機械設備のセンシング―効果的メンテナンスの実現に向けて―(エスカレーター&ホームドア編)」としてまとめ、関係者に配布した。
エスカレーター編では、センサー設置の実態を調査するとともに、利用者の安全に対する意識調査をアンケート方式で行い、効果的なセンサーの種類や取り付け位置についての提案を行った。
ホームドア編では、各鉄道事業者における設置状況の記録写真や設置後の写真などを転載し、今後のホームドアの在り方についての参考とできる様提案した。
また、各社における仕様の差異についてもまとめた。
- エ.昇降機技術小委員会
平成16年度に発刊した「鉄道駅のエスカレーターハンドブック」の見直しを行い、新しい技術の導入や提案を含めた「新・鉄道駅エスカレーターハンドブック」を発刊した。
構造・更新・管理の視点から見直しを行ったが、構造では前回からより進化した技術の紹介や構造の細部に至る説明をし、鉄道駅に相応しい構造について提案した。更新では、更新の仕方の決定を各プロセス毎に記載するとともに、より効率的な更新方法について提案した。管理の視点からは、特に問題となっている転倒事故防止に照準をあて、その対策等を記載した。
- オ.ホームの安全確保技術小委員会の設立
機械設備メンテナンス技術小委員会のホームドアワーキングを本小委員会に 分離する形で新たに小委員会を開催し、今後の活動方針について検討した。
(3) 電子図書館の構築
11月20日に第3回電子図書館構築委員会を開催し、収蔵図書の在り方、システム仕様書などについて検討を行った。
その結果を踏まえ、協会内に「システム構築業者選定委員会」を設置し、委員から推薦のあったシステム構築業者数社からプレゼンテーションを受け、検討を重ねて1社を選定した。
また、蔵書を電子図書館に収蔵するにあたり、著作者に電子化と公開について同意を得ることが必要となるが、協会誌「R&m」に於いても例外ではなく、電子図書館収蔵対象とした「研究と開発」「業務研究」「メンテナンス」の各項目について2001年1月号から2012年3月号までの掲載記事の執筆者延べ約3,300人を同意書対象とした。しかし、2013年3月31日現在の同意書回収率は約38%と低い状況であるため、今後ホームページを活用するなどあらゆる場面で回収率をあげることを実施するが、引き続き会員のご協力を得たいと考えている。
なお、2013年度中に開設する時点での協会誌「R&m」の電子図書館収蔵対象論文は、2011年3月号までのものとし、その後は1年経つ毎にその1年分を一括収蔵していくことを考えている。また、2012年4月号以降のものは著作者に原稿依頼と同時に同意を得ることで進めている。
[ 受託事業 ]
平成24年度の主な受託研究は、以下のとおりである。
(1) 鉄道及び軌道の技術基準の運用状況等に関する調査検討(車両関係)
鉄道に関する技術基準の見直しに関して、有識者や鉄道事業者からなる「鉄道部会」、「気動車部会」、「地方部会」の3部会を設置し、運用状況を調査検討して報告書を提出した。「地方部会」については、地方鉄道の業務に大いに参考になる研修関係のマニュアルも作成した。
(2) 気動車の技術検討及び評価委員会(エンジン・変速機の検査内容見直し)
気動車のエンジン・変速機の検査内容を見直すために、有識者やJRの実務者からなる委員会を設置し、試験車によるデータ収集等による現状分析や評価方法等を検討した。
(3) 次世代エスカレーターに必要な機能・構造に向けた技術調査
受注内容に則り、工期どおり報告書をまとめ竣功した。
(4) コンテナ貨物輸送システムの調査研究
諸外国と我が国のコンテナ貨物輸送システムについて、以下の項目を主とした比較調査を行った。
- ・外国におけるコンテナ陸上輸送体系
- ・外国における鉄道輸送と道路輸送の関連
- ・鉄道輸送事業者と道路輸送事業者の経営的関連
- ・物流斡旋事業者、機材類の調達、提供事業者の相互関連
- ・新形式車両、新形コンテナの開発、検討
- ・編成両端動力車の固定編成(貨物電車方式)の推進
(5) 危険品貨物輸送の基本に関する調査研究
鉄道による危険品輸送の営業促進と安全確保のため、運送約款、規程類を中心として実務的な取扱い方を解説した技術教育用資料を作成した。作成に当たっては、社内外に対する講習、教育、説明用に供するほか日常業務の必携として活用できることも考慮した。
2.技術認定講習・試験事業
車両関係及び機械関係の工事施行技術者に対する資格認定のため、講習会及び認定試験を実施した。
平成24年度は、車両関係では新規560名(対前年51名増)、更新950名(対前年88名減)の計1,510名(対前年37名減)が、機械関係では新規1,361名(対前年226名増)、更新2,313名(対前年102名増)の計3,674名(対前年328名増)が受験した。
3.鉄道車両用材料燃焼性試験事業
車両用材料燃焼性判定試験は、1,358件(コーンカロリーメータによる試験77件を含む)であった。
4.教育及び知識普及事業
(1) 全国「車両と機械」研究発表会及び特別講演会の開催
優秀な論文と提案の研究発表会への参加をJRはじめ、民営鉄道、公営鉄道及び関連グループ会社並びに関連メーカーに呼びかけた結果、応募論文が57件、応募提案が19件あった。応募論文は発表論文選考委員会において20件を、発表提案は事務局において5件を選考し、平成25年2月14、15日に発表会を開催した。
発表後、審査委員会を開催し、論文では最優秀賞1件、優秀賞2件、優良賞2件、特別賞2件、奨励賞13件を、提案では優秀賞1件、奨励賞4件を表彰した。発表会の参加者は493名であった。
また、審査委員会の審議時間を活用して特別講演会を開催し、東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所 次長 鎌田 雅己 様から「甦った東京駅丸の内駅舎 ~保存・復原の全貌を語る~」の講演をいただいた。
(2) 「車両と機械」技術セミナーの開催
鉄道固有技術及びその周辺技術に関するテーマ8件を選考して、計4回、9月6日、10月4日、11月1日、12月6日に開催し、JR東日本、東京メトロ、名古屋鉄道、JR九州、JALエンジニアリング、三菱重工、東武鉄道と東武エネルギーマネジメント、当協会 機械委員会 昇降機技術小委員会の皆様方から講演をいただいた。聴講者は延べ289名であった。
(3) 「機械技術セミナー」の開催
鉄道事業者及びその協力会社の若手機械関係社員を対象に、企画力育成を目指した「機械技術セミナー」を平成24年11月29日から30日に開催し、13名が参加した。
(4) 鉄道設計技士「試験区分 鉄道車両」受験対策講習会の開催
鉄道設計技士(鉄道車両部門)試験の受験準備を目的に、分野別専門講師による講習会を7月21日(土)に開催し、35名が受講した。
(5) 専門技術研修の開催
平成23年度に出版した鉄道電気車両主回路シリーズ「主回路システム」を教材とした専門技術研修を東京地区で10月24日に、関西地区で1月29日に開催した。受講者は計55名であった。
(6) 第17回海外鉄道調査団の派遣
Inno Trans 2012 の開催に合わせて、ヨーロッパにおける最新の技術、新しい機械設備の導入等、鉄道車両と鉄道駅機械設備の状況、コンテナ輸送の状況の調査を、9月19日から28日の10日間の行程で、車両・機械班19名、貨物班9名の計28名を派遣して行った。この結果を報告書にまとめ、平成25年2月27日に報告会を開催し、29名が参加した。
5.刊行物発行事業
(1) 協会誌「R&m」
幅広い読者層に親しまれる技術専門誌として、新しい研究開発の紹介や技術解説、現場で抱える技術課題などを掲載し、充実した内容、判りやすい記述、タイムリーな情報掲載に努めてきた。平成24年度から各記事について電子図書館へのデータ提供の可否を確認させていただくこととした。
また、2月の編集委員会で、平成24年中の「R&m」誌から優秀記事の選定を行った。
(2) 鉄道電気車両主回路シリーズ
進歩の著しい最新車両技術の代表的な主回路及びその関係機器を対象に、JR西日本殿からの受託事業により平成21年度までに纏めた報告書を元に、車両委員会の「技術継承部門」において検討し、「鉄道電気車両主回路シリーズ3(主電動機編)」として出版した。
(3) 新・鉄道駅エスカレーターハンドブック
平成16年度に刊行した「鉄道駅のエスカレーターハンドブック」の発行後に顕在化した新たな課題や更新時期を迎えるエスカレーター取り換え工事の施工方法等について機械委員会の下の小委員会のワーキンググループで検討を進め、「新・鉄道駅エスカレーターハンドブック」として4月に出版した。
6.表彰
平成24年6月20日の定時総会で、平成23年度の功労賞19名、功績賞3名、優秀技能賞28名と、平成23年中の「R&m」掲載記事の中から選考された優秀賞5件、特別賞1件の寄稿者を表彰した。
また、平成25年3月27日に開催された表彰選考委員会で、平成24年度の功労賞20名、功績賞4名、優秀技能賞30名が、平成25年2月のR&m編集委員会で、平成24年の「R&m」掲載記事の中から優秀賞5件、特別賞1件が選考された。これらの方々に対する表彰は、平成25年度定時総会後の表彰式で行う。
なお、平成24年度の全国「車両と機械」研究論文発表会における優秀論文・提案の表彰は、平成25年2月14、15日に実施された発表会後に実施済である。
7.設立20周年記念事業
平成25年は当協会の設立20年の節目の年を迎える。その記念事業として平成24年度は具体的な事業の内容の検討を行い、記念式典として講演会、協会に貢献された方への感謝状贈呈式、祝賀会を行うこととし、そのスケジュールを決めた。
それと平行して、「20年のあゆみ」の刊行に向けて執筆・編集を進めた他、若年会員を対象とした各支部の特徴を踏まえた支部別国内研修の検討や海外研修の検討を行った。
8.会員の現状
各支部関係者等の尽力の結果、平成25年3月末現在の団体正会員は925社(対前年度5社増)、個人正会員は6,780名(対前年度127名増)となった。