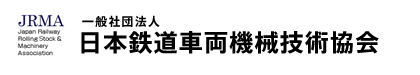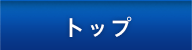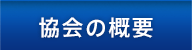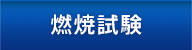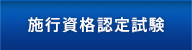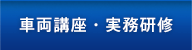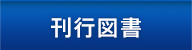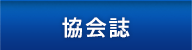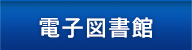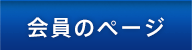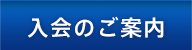活動実績
業務活動実績
21年度の業務活動実績
1.調査研究及び試験事業
[ 自主事業 ]
(1) 車両関係
- ア.「解説 鉄道に関する技術基準(車両編)改訂版」のトレースと次回改訂への準備
今年度には「解説 鉄道に関する技術基準(車両編)」改訂版がどの様に利用されているのかを調査する為、作業部会を通じてアンケートを実施した。
- イ.鉄道事業者共通課題の調査検討
関東・中部地区の車両担当課長を中心に定期的な連絡会議を、2ヶ月に1回開催し、技術情報、保守情報、故障情報などの活発な情報交換を行った。新たに、下期から関西地区の車両担当課長連絡会を関西支部が主催して開始した。
- ウ.車両工事資格認定制度の見直し
車両工事資格認定制度に関して、必要な制度の見直し改善等の検討を行なった。
- エ.技術図書・資料の電子化
従前に引き続き、車両設計技術・メンテナンス技術の継承を目指して、技術図書・資料の電子化(PDFファイル化)に取り組み、電子資料の蓄積を進めてきた。
(2) 機械関係
- ア.機械企画小委員会
教育および知識普及活動の一環として、若手機械関係社員を対象とした技術伝承についての検討を進めた。
- イ.エネルギーマネジメント技術小委員会
地球温暖化問題の益々の高まりの中、エネルギーマネジメント技術への更なる取組みについて次の項目を抽出し検討を進めた。
1. 省エネルギー技術の先進的な取り組み事例の収集
2. 最新事例から見る、大・中・小規模空調設備の運転技術・方法収集
3. 今後の空調設備の在り方や、再生可能エネルギーへの取り組みなど- ウ.機械設備メンテナンス技術小委員会
対象機種を、エスカレーター、ホーム可動柵に限定し、モニタリングシステムの在り方と保全業務への活用策について研究し、今後のメンテナンス手法の革新に向けて検討を進めた。
- エ.昇降機技術小委員会
テーマを「鉄道駅の特性に適した昇降機(エスカレーター)の在り方」とし、平成16年度に刊行した「鉄道駅のエスカレーターハンドブック」の発行後に顕在化した昇降機に関する新たな課題や、未解決の課題について取り組みを進めた。
また、鉄道事業者へのアンケート結果から、更新時期を迎えるエスカレーターについて、WG形式で検討を進めた。検討結果については、22年度以降に「鉄道駅のエレベーターハンドブック(改訂版)」として発行する予定である。
(3) 輸送技術関係
- ア.「コンテナによる鉄道貨物輸送の手引書」の作成
JR貨物におけるコンテナ関係規定類の整備を踏まえ、荷主、私有コンテナ所有者、メーカー、代理運送業者、コンテナ輸送業務担当者等を対象とした、「コンテナによる鉄道貨物輸送の手引書」を作成して発行した。
[ 受託事業 ]
(1) 鉄道及び軌道の技術基準の運用状況等に関する調査検討(車両関係)
企画競争入札に応募して、受託契約を締結した。「鉄道」部会では、平成18年度以降の技術基準の見直し等を次回改正時に反映させるための案文審議を行なうと共に、速度計のJIS改訂に伴う技術基準の改正関係について審議した。「軌道」部会では、性能規定化を目指した新省令案の最終案文の審議を行った。新しく、「地方鉄道における車両の構造及び維持管理のありかた」について部会を設置し、該当する地方鉄軌道事業者に対して、車両基本事項及び技術上の課題についてアンケート調査を行い、課題抽出等の検討を実施した。
(各鉄道事業者:継続)(2) 民営鉄道事業者の技術支援(車両関係)
輸送高度化補助金申請に必要な「第三者機関技術評価」調査依頼に、積極的に対応してきた。今年度は、上期に京福電鉄(株)、岳南鉄道(株)、信楽高原鉄道(株)の3社の調査を、下期には長良川鉄道㈱の調査を実施した。
(JR西日本:継続)(3) 「車両用主回路機器 選択設計と保守のマニュアル」の作成(その3)
3ヶ年計画の最終年度であり、カム軸式主制御装置、チョッパ制御装置、インバータ装置、インバータ・コンバータ装置などの主回路電力機器とともに、主回路システム全体を対象として検討を進めた。3月に3分冊に分けたマニュアルを報告した。
(東日本トランスポーテック:新規)(4) SL検修マニュアル教本の作成委員会
JRを中心に運行されているSLの検修技術を、今後の世代に継承し保守マニュアルとして活用できるよう体系的にまとめたハンドブックを作成する。C6120号機の復元業務に併せて、今年度から3ヵ年計画で教本を作成する。
(5) 「次世代エスカレーターの開発に向けた調査研究」
駅のエスカレーターは、利用者数、稼動時間などの負荷や走行利用などの利用状況に起因した障害事故・故障が発生している。しかし、これら事象に対して商業施設と同等の機能・機構のエスカレーターを改良し対応してきたのが現状であり、駅舎専用の機能・機構を有するエスカレーターは存在しない。そこで現状のエスカレーターの機能・機構の見直しを行い、挟まれや緊急停止による転倒のリスクのない駅舎向けエスカレーターの開発に向けての、駅のエスカレーターに求められる機能・機構の仕様化を目的とした調査研究を行なってきた。
(JR貨物:新規)(6) コンテナ貨車の保守とコンテナ輸送体系の関連に関する研究
コンテナ貨車の稼働率改善のため、コンテナ輸送システムと保守体系の関連を調査し分析を行った。
2.技術認定試験事業
車両関係及び機械関係の工事施工技術者に対する資格認定の為、講習会及び認定試験を実施した。平成21年度は、車両関係の受講者は1,409名であり、機械関係では3,000名であった。
3.車両用材料燃焼性試験事業
年度当初は車両用材料燃焼性判定試験を約1,000件で計画した。試験依頼は当初計画より増加し、今年度の実績としては1,116件(コーンカロリーメーター試験51件を含む)となった。
4.教育および知識普及事業
(1) 全国「車両と機械」研究論文発表会および特別講演会の開催
多くの優秀な論文が寄せられるよう、JR各社を始め、民営鉄道、公営鉄道および関連メーカーにも参加を呼びかけた。その結果、応募件数は論文の部で46件、提案の部で16件であった。研究発表会を2月4~5日に開催し、論文部門で20件の発表を行い、最優秀賞1件、優秀賞2件、優良賞2件、特別賞2件を選定して表彰した。提案の部では、5件の発表を行い、優秀賞1件が表彰された。特別講演として、日立製作所から「英国鉄道事業への挑戦と世界鉄道市場の動向」の紹介が行なわれた。
(2) 「車両と機械」技術セミナーの開催
今年度も鉄道固有技術およびその周辺技術に関する8テーマで、計4回にわたって実施した。平成21年度は、ジェイアール東日本コンサルタンツ、JR東日本、小田急電鉄、阪急電鉄、JR西日本などの各社から、それぞれの固有技術の紹介が行なわれた。
(3) 「機械技術セミナー」の開催
鉄道事業者及びその協力会社の若手機械関係社員を対象に、企画力育成を目指した「機械技術セミナー」を開催した。JR各社から、1~3名の参加が見られ、経験豊富な講師からの講義と自主討論などを行い、有意義な教育の場を提供することが出来た。
(4) 鉄道設計技士「試験区分 鉄道車両」受験対策講習会の開催
鉄道設計技士(鉄道車両部門)試験の受験準備を目的に、分野別専門講師による講習会を7月25日に開催し、31名の参加を得た。
(5) 第14回海外鉄道調査団の派遣
今年度は、欧州の高速鉄道、都市鉄道、駅の機械設備、ICカードの状況、の実態などの視察を中心に、10月4日~15日に派遣した。参加者は事務局を含めて16名。報告書をまとめた上で、2月23日に報告会を実施した。
5.刊行物発行事業
(1) 協会誌「R&m」
幅広い読者層に親しまれる技術専門誌として、新しい研究開発の紹介や技術解説、現場でかかえる技術課題などを掲載し、充実した内容、判りやすい記述、タイムリーな情報掲載に努めてきた。1月号から、身近な話題を提供する「なんでもNews」を開始した。また、2月号の編集委員会の場で平成21年中の「R&m」誌から優秀記事の選定を行なった。
(2) 経験から学ぶ車両技術者必携シリーズの刊行
既刊のシリーズ①電気連結器編、及びシリーズ②継電器編に引き続き、今年度は第3巻となる「検知器 センサのはなし」を監修出版した。
(3) 機械関係者連絡名簿
上記名簿の平成21年度版を、8月に発行した。
6.表彰
表彰選考委員会で選考を行い、功労賞20名、功績賞2名、優秀技能賞29名の決定を行なった。平成22年度総会後の表彰式で表彰する。また、全国「車両と機械」研究発表会における優秀論文・提案の表彰は実施済みで、「R&m」優秀記事については前記表彰式の場で表彰する。
7.一般社団法人の見直し
公益一般社団法人の取得に向けた協会定款の変更案を策定し、平成22年5月開催予定の総会に議案として提出している。
8.会員の現状
各支部担当者の尽力もあり、平成21年度末の実績で前年度と比較して、団体正会員は7社減の907社、個人会員は384名増の6,500名となった。
9.協会本部の人の動き
平成21年5月開催の総会において、専務理事の佐々木拓二が退任し、新たに坂本龍治が選任された。