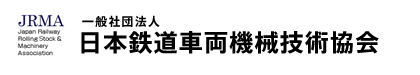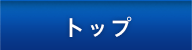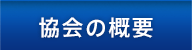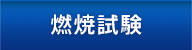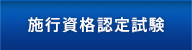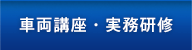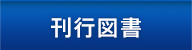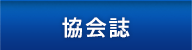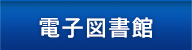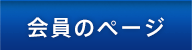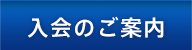活動実績
業務活動実績
22年度の業務活動実績
1.調査研究及び試験事業
[ 自主事業 ]
(1) 車両関係
- ア.鉄道事業者共通課題の調査検討
関東・中部地区の車両担当課長を中心とした14社で構成した連絡会議を2ヶ月に1度開催し、鉄道の故障状況・対策等に関する情報交換を行った。
関西地区では、関西支部が主催して6社からなる車両担当者連絡会を3回実施し、車両検修に係る情報交換を行った。
また、全国の公民鉄15社が参加した車両関係部長会議を1回開催し、車両の国際標準等について情報交換等を行った。- イ.電子機器等の誤動作防止に関する研究会への協力
-
国土交通省の主催で設置された電子機器等の誤動作防止を目的とした研究会において、当協会は事前のデータ分析を行った。
- ウ.技術図書・資料の電子化
従来に引き続き、過去の貴重な図書も含めた各種技術資料の電子化 (PDFファイル化) を、将来の電子図書館のデータベースの一部とすることも考慮して進めた。
(2) 機械関係
- ア. 機械企画小委員会
教育及び知識普及活動の一環として、若手機械関係社員の技術伝承を対象とした「機械技術セミナー」を11月4~5日に実施し、14名が参加した。
- イ. エネルギーマネジメント技術小委員
地球温暖化問題の益々の高まりの中、エネルギーマネジメント技術への更なる取り組みについて、以下の項目を抽出し、検討を行った。
1. 省エネルギー技術の先進的な取り組み事例の収集
2. 最新事例から見る大・中・小規模空調設備の運転技術・方法の収集
3. 今後の空調設備の在り方や、再生可能エネルギーへの取り組みなど- ウ.機械設備メンテナンス技術小委員会
検討の対象をエスカレーターとホーム可動柵に限定し、モニタリングシステムのあり方と保全業務への活用策について調査研究を行った。
- エ.昇降機技術小委員会
平成16年度に刊行した「鉄道駅のエスカレーターハンドブック」の発行後に顕在化した昇降機に関する新たな課題や未解決の課題について対策の検討等の取り組みを進めた。
また、鉄道事業者へのアンケート結果から、更新時期を迎えるエスカレーターの検修等について、ワーキンググループ形式で検討を進めた。
検討結果は、平成23年度以降に「鉄道駅のエスカレーターハンドブック (改訂版) 」として発行する予定である。- オ.鉄道駅のエスカレーター事故防止プロジェクト
鉄道駅におけるエスカレーターの転倒等の事故撲滅に向けて、事故の現況とその対策について集約し、わかりやすいパンフレット等を作成した。
現在、これらの資料を活用し、あらゆる機会を捉えて事故防止に幅広く活動を行っている。
[ 受託事業 ]
(1) 鉄道及び軌道の技術基準の運用状況等に関する調査検討(車両関係)
鉄道に関する技術基準の見直しに関する調査研究について、公開競争入札に応募し、受託契約を締結して検討を行った。
有識者や鉄道事業者からなる「鉄道部会」「軌道部会」「地方部会」の3作業部会を設置し、合計9回開催して運用状況を調査研究し、報告書を提出した。
(2) 気動車の技術検討及び評価委員会(エンジン・変速機の検査内容見直し)
エンジン・変速機の検修方法の見直しに関する委員会と幹事会を各4回開催し、現状分析や評価方法等を検討した。具体的には、装置・部品の検修に関する制約因子の分類、その因子の調査・測定方法の検討とデータ収集用の試験車を決めた。
(3) SLメンテのための技術教本の作成に関する付帯業務
SL (蒸気機関車) の検修技術を今後の世代に継承することを目的として、教材マニュアル作成に関する委員会及び作業部会を設置し、編集を進めた。
(JR貨物:新規)(4) 貨物鉄道長期ビジョンの研究
現行のコンテナ輸送システムを分析し、技術的な課題も含めて中長期的な輸送体系のあり方を研究し、報告した。
(JR貨物:新規)(5) 貨車の技術教育資料の編集
コンテナ貨車についての技術資料を分析して、技術教育に必要なデータベースを作成した。
2.技術認定試験事業
車両関係及び機械関係の工事施行技術者に対する資格認定のため、講習会及び認定試験を実施した。
平成22年度は、車両関係では新規538名、更新953名の計1,491名が、機械関係では新規1,076名、更新1,926名の計3,002名が受験した。
3.車両用材料燃焼性試験事業
年度当初は車両用材料燃焼性判定試験を1,000件 (コーンカロリーメータによる試験50件を含む) で計画したが、1,192件 (コーンカロリーメータによる試験80件を含む) と増になった。
4.教育及び知識普及事業
(1) 全国「車両と機械」研究発表会及び特別講演会の開催
優秀な論文と提案の発表参加を、JR各社を始め、民営鉄道、公営鉄道及び関連グループ会社並びに関連メーカに各所で呼びかけた結果、全国から49件の論文と14件の提案の応募があった。その中から20件の論文と5件の提案の合わせて25件を選考し、2月17、18日に発表会を行った。
発表後、審査委員会を開催し、論文では最優秀賞1件、優秀賞2件、優良賞2件、特別賞1件、奨励賞14件を、提案では優秀賞1件、奨励賞4件を表彰した。
発表会の参加者は542名であった。
また、審査委員会の審議時間を活用して特別講演会を開催し、近畿車輛株式会社から「近畿車輌の海外案件への取り組み」の紹介を行った。
(2) 「車両と機械」技術セミナーの開催
技術セミナーは、9月から12月に計4回にわたって、JR東日本、京成電鉄、南海電鉄、東芝などの会社から各社の鉄道に関する固有技術やその周辺技術に関する8テーマについて実施した。聴講者は延べ303名であった。
(3) 「機械技術セミナー」の開催
鉄道事業者及びその協力会社の若手機械関係社員を対象に、企画力育成、技術継承を目指した「機械技術セミナー」を開催し、JR各社から14名が参加した。
(4) 鉄道設計技士「試験区分 鉄道車両」受験対策講習会の開催
鉄道設計技士 (鉄道車両部門) 試験の受験準備を目的とした分野別専門講師による講習会を7月24日に開催し、JR各社等から33名の受講者があった。
(5) 第15回海外鉄道調査団の派遣
ベルリンで開催された「イノ・トランス2010」への参加、ドイツ鉄道・フランス国鉄・フランス空港公団への訪問、ベルリン中央駅やブリュッセル・リールなどの鉄道駅の視察、高速車両のICE・タリス・ユーロスター・TGVの試乗を目的に、9月21日~30日の10日間の派遣を行った。
参加者は事務局を含めて16名で、報告書をまとめて、2月25日に報告会を開催した。報告会には24名が参加した。
5.刊行物発行事業
(1) 協会誌「R&m」
幅広い読者層に親しまれる技術専門誌として、新しい研究開発の紹介や技術解説、現場で抱える技術課題等を掲載し、内容の充実、分かりやすい記述等に努めてきた。平成21年度から始めた身近な話題を提供する「なんでもニュース」欄の投稿が増えている。
また、2月の編集委員会で、平成22年中の「R&m」誌から優秀記事の選定を行った。
(2) 鉄道電気車両主回路シリーズ
平成21年度までJR西日本殿からの受託事業で製作した主回路システム等を対象とした「選択設計と保守のマニュアル」について、同社のご理解とご協力を得て全国の関連業務従事者の技術力向上を目的とし、鉄道電気車両主回路シリーズの「主回路電力変換装置-インバータ・コンバータ-」と「主回路システム」の2冊を出版した。
(3) 機械関係者連絡名簿
機械関係者名簿の平成22年度版を8月1日に1,100部発行し、9月に完売した。
6.表彰
平成22年5月27日の総会で、平成21年度の功労賞20名、功績賞2名、優秀技能賞29名と、「R&m」掲載記事の中から選考された優秀賞5名、特別賞1名の方々を表彰した。
平成23年3月24日に開催された表彰選考委員会で、平成22年度の功労賞20名、功績賞3名、優秀技能賞30名が選考された。また、平成23年2月のR&m編集委員会で、平成22年の「R&m」掲載記事の中から優秀賞5件、特別賞2件が選考された。これらの方々に対する表彰は、平成23年度総会後の表彰式で行う。
なお、平成22年度の全国「車両と機械」研究論文発表会における優秀論文・提案の表彰は、2月17、18日に実施された発表会で実施済である。
7.公益法人の見直し
昨年の総会でご承認いただいた公益一般社団法人への移行に向けて種々の準備を、公益認定等委員会事務局との折衝等を通して進めてきた。しかし、一部の公益目的事業が当協会の活動方針等に合致しないため除外せざるを得なくなったこと、それに伴い公益一般社団法人としての経理的要件が達成できない可能性があることが明確になったため、本総会の別議案にあるように公益一般社団法人の申請の取り下げを行う予定である。
8.会員の現状
各支部担当者等の尽力の結果、平成23年3月末の実績で、団体正会員は914社 (対前年度7社増) 、個人正会員は6,621名 (対前年度121名増) となった。
9.協会本部の組織の変更
平成22年7月1日に協会本部の組織の変更を行い、企画部を廃止し、研修部を新設した。